戦後日米文化交流の変遷―ジェンダーの視点から―
越智淳子

本日は、雨の中、わざわざお出かけ下さいましてありがとうございました。
今日は、日米文化交流の変遷―ジェンダーの視点から―というタイトルで話を進めてまいりますが、このタイトルから、日米文化交流の変遷とジェンダーがどう関わるのか・・と疑問に思われる方も多いかと思います。そもそもジェンダーという言葉自体、わかりにくいですね。更に日本では、1975年の国連婦人年から1995年の北京女性会議で各国に女性の地位向上のためのナショナル・ボディ(国家機構)を設立する目標を設定した際、おそらくは外来語の概念が分かりにくかったというのが主な要因でしょうが、ジェンダーを使用するかどうかでずいぶん問題になったと聞いています。結局、ジェンダー・イクォリティ(男女平等)という言葉を、男女共同参画社会と呼称することで、現在、内閣府には男女共同参加局が置かれて、男女共同参画社会の促進を図っています。それでは、今日のタイトルを「戦後日米文化交流の変遷―男女共同参画社会の視点から―」として良いか・・というと、これまた、私の意図するところからは大分離れてしまいます。私が意味するジェンダーとは、もっとシンプルな、思考を整理するためのツールとでも言えるものです。私は「ジェンダー」を、ここでは行動のためというより、認識の手段として使っている・・ということをご理解願います。
ジェンダーという言葉は、もともとは、グラマティカル・ジェンダーというような、言語の中の文法上の性という地味な領域の言葉でした。例えばフランス語では海、ラ・メールは女性名詞で、太陽、ル・ソレイユは男性名詞ということで、冠詞も性によって変化するわけですが、このような文法の性差を示す言葉がジェンダーの主な使われ方でした。言語に性別の無い日本語を使う我々は、つい、この性差はイメージで決まるのか・・と思いがちですが、純粋に発音上の問題なのだそうですね。ちなみに英語には、言葉の性別がありませんから、必修外国語が英語という日本人には大いに助かっていると思います。
それでは、今日使われているジェンダーとはどの辺から始まったかといえば、スイス系の米国人で社会心理学者のジョン・マニーが、Gender as a role(役割としての性)という概念でジェンダーという言葉を50年代半ば頃に使い始めたと言われています。ちょうど米国では60年代から盛んになってきた市民権運動やフェミニズム運動の理念に、この「役割として性の概念が適用されてきたわけです。性―セックスという言葉は、男女それぞれ単一の性を示し、また関係性を示すのに比べて、ジェンダーは「性差」あるいは「性別」を表現するのにより相応しいからとも思われます。米国の60年代から70年代における社会状況の急激な変化と共にジェンダーという言葉も、脚光を浴びるようになったわけです。

それでは日本で、ジェンダーが男性を含めて有識者層に、新しい概念として関心が向けられる一つのきっかけとなったのは、私の考えでは、イヴァン・イリイチの思想が紹介された80年代初頭ころではないかと思っています。イリイチは、オーストリア人で元カソリックの神父でしたが、開発問題でバチカンとの見解に異議を唱えたため、バチカンから追放され、後に哲学者、文明批評家として活躍し、2002年に亡くなりました。彼が1980年12月に横浜で開催された「アジア平和研究国際会議」で講演した記録とエッセイを翻訳した「シャドウ・ワーク」という本があります(注1)。その中で、イリイチは、例えば女性が主たる担い手である家事労働を経済活動の目に見えない労働として「シャドウ・ワーク」(影の労働)と名付けました。シャドウ・ワークは、例えばスーパーで買い手自らが品物を袋に入れる行為なども入ります。そして、彼は、男性は勤労者で主婦は消費者・・という構図は、管理された現代産業社会の典型例であるとしています。そして、その構造は、男性、女性に限らず、人間の自立性を妨げるものだと批判しています。彼は、ジェンダーという言葉を盛んに使っていますが、現代は、むしろ自立性の欠如が問題であり、ジェンダーレス社会、ジェンダーレス人間を生み出しているとも批判しています。かといって、イリイチは、男は狩り、女は竈・・というありきたりのジェンダー役割を支持しているわけではありません。率直に言って、イリイチの思想は、決して単純ではなく、理解するのに難しいところがありますが、近代の開発・発展そして現代の産業社会に根本的な問いかけを行っているという点で、決して見過ごすことができない、それだけでなく、今日では、益々重要性が増してくる思想家ではないかと思います。
さて、ジェンダーという言葉の問題は、この辺にして本題に入りたいと思います。タイトルには戦後とありますが、戦後という言葉を時間軸で少し考えてみたいと思います。最近の若い人たちは、古さをからかう時に「昭和だなあ・・」と言うようですが、ご存知のように昭和は非常に長いものですから、私の世代にように「戦前と戦後」という時代区分が、ごく当たり前になっている者にとっては、平成の人たちが言う「昭和」は昭和30年代をイメージしているようですが、戦後の過渡期である「昭和30年代」で、昭和をひとくくりに語ることはとても出来ない・・と思います。では、我々世代には慣れ親しんだ戦前と戦後の二分法で行きますと、昭和は62年と14日間続きましたので、ほぼ、その三分の一が戦前で、三分の二が戦後ということになります。ところが、昭和元年1926年から昭和20年1945年の間は、昭和6年の満州事変、昭和12年の日中戦争、昭和16年の太平洋戦争とずーっと戦争がつづいていたわけでして、戦前というよりは戦中と呼んだ方が正確かと思います。つまり、戦前と戦後の二分法もまた、アメリカとの戦争だけが戦争であったかような錯覚を生み出しているとも言えるでしょう。この錯覚は、今もって解消されたとは言い難いところがあります。もっとも、本土が実際の戦闘に巻き込まれることなく、戦争が外国で続いている間は、本国に暮らす人々にとっては実感が無い・・ということはある程度事実かもしれません。私がオレゴン州のポートランドで暮らしていた頃は、対イラク戦争が続いていまして、戦争反対の声はかなり強くありましたが、戦争自体は、家族を兵士として送り出している家族以外の人々の日常生活には、目立った影響も無く、実感は薄い・・というのも現実でした。ところが、膨大な戦費のような実体的な影響は、目に見えないだけで、時差で、後から生活にも襲ってくるのです。しかし、この戦争当事国と言う実感が薄いという経験は、昭和戦前期の日本人の生活というものを私により実感的に想像させる契機にもなりました。

それでは、日米が戦争に入る前と入った後の期間の日米の政府同士は、相手をどう認識し、どう対策をとってきたか・・ということを非常に単純な比較ですが、示してみます。米国は、対日敵視政策ラインとして、まず日本人を観察と研究の対象としました。具体的には、日本の情報を収集すること、そして日本研究の専門家を作ること、そのために、優秀な学生を集めて短期集中的な日本語学習を課しました。戦後、このグループから、源氏物語を翻訳したサイデンスティッカー、日本文学を世界に紹介し遂に日本に帰化したドナルド・キーン氏、あるいは社会学ではドナルド・ドーア氏など、多くの逸材を輩出しました。また、ルーズベルト大統領は、文化人類学者のルース・ベネディクトに日本人研究を命じて、その成果が「菊と刀」ですが、彼女は一度も日本の土を踏まずに、文献だけでこれを書き上げました。この事実は、今日では、感嘆する一方、疑問にも思えるという、日本人にはある種の複雑な感情をもたらしますが、戦後、この本が、日本の有識者層にとっては、外国からの視点が、結果的に自己認識の手段ともなったことは事実ですし、また、この「菊と刀」は今なお欧米人の対日観に影響を与えていると言っても過言ではないでしょう。
では、日本の対米認識はどうだったか?日本では、アメリカ人を文化人類学的アプローチで、研究の対象にした・・という学問的成果はあったとは言えません。また、英語を集中的に学習させるどころか、むしろ、全く逆な、敵性語として学校での英語学習を廃止したのです。この英語拒否時代に学生だった世代が、戦後間もなく外交官になった当初、非常に苦労したと述懐するのを聞いたことがあります。
米国では、戦争の勝利が目的であり、また既に勝利の展望もあり、戦後の占領政策まで計画されていました。一方、日本は、戦闘の勝利という当面の目的だったことと、いわゆる「大東亜共栄圏」構想は、敗戦と共に消え、どの程度具体性があったのかどうかさえも歴史的に検証されていません。
これは、私の推測ですが、アメリカが日本人を研究の対象にしたのは、ある意味、日本人を知らないことに自覚的だったのではないかと思います。一方、日本人は(といっても都市住民ですが)戦争の開始直前までハリウッド映画を楽しんでいて、自分たちがアメリカのことを知らないとはあまり思ってはいなかったのではないでしょうか?もっとも、この比較では、主体になるのが、米国は政府で、日本は一般人になるわけですから、比較としてバランスが取れているとは言えません。でも、当時の日本政府の対米認識がどのようであったかについては、これまでもアカデミックな研究成果というものを、私の勉強不足とは思いますが、一般的に知られているわけでもないような気がします。
では、日米が戦争中の女性の姿は、どうだったのでしょう。個々人の生活はさておき、戦争遂行という国家目的のためには、両国政府とも女性を動員しました。米国は、この”Rosie, Riveter”(リベット(鋲打ち)工、ロージー)と呼びかけ、生産ライン、工場労働者に動員しました。バンダナで髪をまとめた女性が力こぶを見せている上には、We can do it(私たちはできる)の文字が見えます。当時のアメリカのキャンペーン映画には、集まってブリッジを楽しんでいた家庭の主婦たちが突然「そうだ、国のために働きましょう」と言って立ち上がるという、今では笑ってしまうような、いかにも直接的なプロパガンダ映像を見たことがあります。実は、戦争時のこの盛んなキャンペーンが、戦後、復員兵を雇用する段になって、手のひらを返すように、大々的な「家庭へ帰れ」キャンペーンとなったことが、アメリカの戦後の女性運動の伏線になったと唱える女性学研究者もいます。
日本では、「軍国乙女」と呼ばれる、成人女性ではなく、女学生、今の中、高校生にあたる年齢層が工場に動員されたのでした。なぜ日本では、主婦が対象にならなかったのでしょうか?これはきちんと研究する必要があることかと思いますが、ひとつには、戦前の日本では、主婦は、夫を戦地へ送り出した後も舅、姑、子供を抱えた大家族制度を下支えする中心的な存在だったからではないかと思います。主婦が動員されては、家制度そのものが崩壊する可能性があったからではないでしょうか。
さて、戦争は日本の敗戦で終わりました。唐突ですが、これはアイ・ラブ・ルーシーですね。懐かしいと思われる方も多いと思います。郊外に住むルーシーが引き起こすさまざまなドタバタに、大声で笑った喜劇でした。以前、アメリカの再放送で見た面白いエピソードがあります。ある日、ルーシーの近所に日本人女性を妻にしたアメリカ人男性が引っ越してきました。その日本人女性の夫にかしづくことメイドの如くで、隣近所の男性たちは、口をあんぐりと開けて羨ましがることしきり・・夫たちの関心を取り戻すべく、ルーシーたちも、それならば・・と日本人女性の真似を始めます。深々とお辞儀をすれば、おでこをぶつけてしまう、しずしずとお茶を運べば躓いて夫にかけてしまう、夫の背後から上着を着せようとすると、どこがどこやら二人でがんじがらめになってしまう・・と彼女たちの努力はことごとく失敗に終わります。ところが、夫たちは相変わらず日本人妻を羨ましがるばかり。どうしようと妻たちは頭を抱えます。その時、ルーシーがはっとひらめきます。数日後、ルーシーたちが、そっと日本人妻カップルの家を覗いてみると、あのしとやかだった日本人妻は、大変貌していて、がみがみと口やかましく、夫に指図している、夫はおどおどしながら家事をしている姿でした。ルーシーたちは、大喜び、自分たちが成功したことを確認したのです。つまり、アメリカ人女性の日本化は失敗したけれど、日本人女性のアメリカ化には成功したというわけです。この話は、ステレオタイプを逆手にして本当に面白い喜劇になっていますね。それにしても、日本人女性がメイドのように夫にかしづくというイメージは一体どこから来たのでしょう。かつて、そうですね80年代初頭ぐらいまでは続いたでしょうか・・日本人(主に男性ですが)が苦笑とある種の軽蔑を込めてよく口にしたのは「アメリカ人の対日イメージは、ゲイシャ・フジヤマ・ハラキリだ」というものです。富士山が素晴らしく印象的なのは確かですし、ハラキリはショックでしょうが、ではなぜゲイシャなのでしょうか?
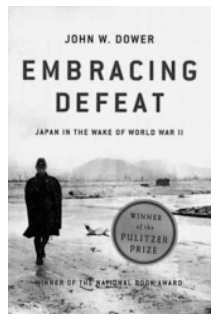
この写真を見て下さい。日本の歴史研究で有名なジョン・ダワーさんの「敗北を抱きしめて」(注2)に掲載されている資料写真です。こちらは、着陸する米軍の飛行機に向けて、日本髪の女性二人が手を振っている後姿です。こちらは、横浜に寄港するアメリカの軍艦の前で、着物姿の女性たちが歓迎の踊りを踊っています。今、この写真を見るとゆるい苦笑がもれそうですが、戦後、これが米国に対する日本のひとつのもてなしの形だったのは確かでしょう。外交に限らず、何らかの交渉の場で、相手の機嫌をとるためのもてなしは、どこの国でも昔から・・というか昔のほうがもっと盛んでしたが、そこで女性にもてなし役を務めさせるというのも、男性中心の社会では、ごく当たり前の習わしだったということでしょう。米国人男性にとって、最初に接する日本人女性が、着物姿で、エキゾチックでとびきりのサービス精神で尽くしてくれる芸者さんたちであれば、ゲイシャが日本のイメージとして浸透定着するのは何の不思議もありません。つまり、日本、あえて言えば日本の男性たちが自ら行ってきた行為の結果として、「ゲイシャ」というステレオタイプのイメージが作られたということです。このことは、多様な層で多彩な接触が可能な現代では、一律の対日イメージというもの自体が、既に影をひそめている事実からも推測できます。
話は変わりますが、フィンランドのもてなしは何でしょうか?そうサウナですね。サウナ外交で、ソ連のフルシチョフ首相をもてなしたことは有名です。自分も裸になり、相手も裸にする・・というもてなしは、確かに否応なく信頼関係を作り上げていくのに、なかなか効果があるのではないでしょうか。
さて、先ほど言及したジョン・ダワー元MIT教授の「敗北を抱きしめて」の中には、こんな写真もあります。こちらは普通のお嬢さんらしい着物姿の日本女性を大勢のアメリカ兵が囲んで、カメラのシャッターを押している図です。そして、これにつけられたキャプションには、日米関係について非常に刺激的かつ深い意味を考えさせてくれます。
「征服者の目に映った日本は、ほぼ即座にエロティシズムの対象とされた。それ以降、仮想的な男らしさと女らしさで作り上げられた複雑な相互役割が、日米関係を色づけてきたのである。」(筆者訳)
このキャプションは、私に日米関係のある種のうまく説明されていないところをジェンダーの視点から考えさせるきっかけになったとも言えます。
日本という国の女性化―という状況は、女性にとっては心理的に左程の抵抗感を生じさせないかもしれない一方、男性心理には抵抗感を伴う可能性が想像されます。この女性としての日本、男性としてのアメリカという日米関係の姿は、既に66年も経っていますから、その間において決して一様ではありませんし、時代ごとにいくつもの変化が見て取れます。この変遷については後で述べますが、まず、戦後の米国の占領政策について見てみましょう。いうまでもなく占領政策の眼目は日本の民主化ですが、ここにアメリカらしい、というか日本ではあまり見られないことがあります。それは民主化の実施機関に、公的機関ではなく、民間団体による貢献が大きかったということです。つまり、民間団体が米国の占領政策に協力したのですが、アメリカの民間団体には、その力、つまり圧倒的資金力あったということを理解する必要があると思います。同時に、フィランソロピー、博愛精神と翻訳されますが、いわゆる慈善活動に通じる精神理念が米国には根付いていて、その精神は、今も、例えば、マイクロソフトで成功したビル・ゲイツは、今ではビジネスよりも、もっぱら自らの財団での慈善活動に集中している・・というように、現在にも継承されているわけです。
占領期の1948年から約30年1975年まで、ロックフェラー財団、カーネギー財団、ロックフェラーⅢ世基金、フォード財団、ロックフェラー兄弟基金、アジア財団、メロン財団他多数の団体等が、それぞれ巨額な資金援助を行ったのです。その日本側の受け手は、政府・各省庁、各国立・私立大学、そしてアメリカ連邦議会図書館をモデルとして設立された国会図書館等々多数に登ります。日本の制度的や知的分野の民主化を進めるためにアメリカの財団が支払った金額は、総額にして約2528万ドル(9200億円)になります(注3)。この間には国際文化会館の設立、フルブライト留学制度による留学生交流などもありました。実にさまざまな分野での交流に、アメリカの気前の良い援助があった事実を、日本人は自己認識のためにも忘れてはいけないと思います。

そして米国政府の占領政策―日本の民主化の最大の眼目が、日本国憲法の制定にあったことは言うまでもありません。私がここで取り上げますのは、日本国憲法の女性に関する第24条についてです。ベアテ・シロタ・ゴードンさんをご存知でしょうか?ベアテさんは1923年ウイーンで生まれました。お父さんは当時有名なロシアのピアニストのレオ・シロタで、ベアテさんが5歳の時、山田耕作の招きで東京音楽専門学校、今の芸大の音楽科で教えるために日本に一家でやってきました。当初は半年ほどの滞在予定が、結局15年近く、ベアテさんは日本で成長した後、大学進学のために米国に行きますが、その間に日米が戦争となり、日本に残っている両親の消息もわからないまま、戦後、ベアテさんは、その日本語能力を買われてGHQの一員として日本にやってきて、両親と劇的な再会を果たしました。ベアテさんの自伝は、ベアテさんがテープに吹き込んだものを日本語に起こして「1945年のクリスマス、日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝」(注4)として1995年に出版されました。そして1997年に出版された英語版はThe Only Woman in the Room(その部屋でただ一人の女性)(注5)というタイトルになっていますが、まさにベアテさんは、タイトル通りの状況下で、憲法草案作成で「女性」を担当するよう命じられたのでした。憲法第24条1.は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が堂々の権利を有することを基本とし、相互の協力により維持されなければならない。」とし、第2項は、両性の本質的平等が謳われています。今日では、当たり前のことが、この憲法第24条で保障されたと言えるでしょう。日本側担当者では、「女性の権利」という観念は、ほぼ無いに等しかったようですが、ベアテさんが日本で育ったという事実を聞かされた日本側は、意外なほどすんなりと起案を受け入れてくれたと、この本には書かれています。戦後、マスメディアでしきりに使われた言葉が「戦後強くなったものは靴下と女」というフレーズでした。子供だった私は、この表現が不思議でなりませんでした。というのも、女性のストッキングは、すぐに伝線するような薄く弱いものでしたから、どこが強いのだろうと不思議だったのです。後年になって、ここでいう靴下は、戦後のナイロン製の男性用ソックスを意味していたことがわかり、確かに男性にとっては、戦前のすぐに穴があく木綿製よりは、画期的な強さの靴下になったためと納得わけです。それにしても、こういう齟齬は、ある意味、男性は男性の、女性は女性の思考や経験の範囲で語っている・・という事実を感じさせられます。
ベアテさんは、戦後は、ニューヨークのジャパンソサエティを率いて、日本文化の米国への紹介に実に精力的に活躍しました。一柳 慧先生も、ニューヨークのジュリアードに留学されていた頃、ベアテさんにご親切にされたとのことで、2008年にNYでコンサートをされた際、私もポートランドから出かけましたが、ベアテさんがいらして、お二人の思い出を語る対談もありました。ベアテさんについては、ドキュメンタリーが二つ制作されていますので、機会を見つけて、是非ご覧ください。
さて、米国の占領期は、サンフランシスコ講和条約を1951年9月に署名して終了しますが、その前の1950年6月25日から朝鮮戦争が勃発し、1953年7月27日の休戦から現在に至っています。そして51年の4月にはトルーマン大統領は朝鮮戦争の方針の違いで、マッカーサー司令官を解任しました。日本人にとって、いわば圧倒的な存在だったマッカーサーが解任されたことは、大変な驚きでした。既に、東西冷戦体制が着々と進む中、日本は1956年10月19日に日ソ共同宣言に署名して、その年の12月18日国際連合に加盟し、国際社会に復帰しました。
ようやく日米の文化交流にたどりつきました。文化交流といっても儀式的でない真の相互影響と新しい創造を生み出す交流は、結局は、芸術家同士、人間同士の交流になります。例えば、一柳先生は、米国の最新鋭のジョン・ケージの音楽を日本に紹介して、日本の音楽界を驚嘆させました。武満徹は、ニューヨークで日本の音を響かせて新線な新たな音楽の刺激をもたらしました。指揮者の小澤征爾は、ボストン・フィルの監督を長く勤めました。文学では、戦後詩を代表する詩人大岡信は、画家で詩人のサム・フランシスとの交流を実現しました。大江健三郎、石原慎太郎も、ノーマン・メイラーやカポーティなどのアメリカ文学に新鮮な影響を受けたはずです。1950年代から活動しはじめたこの世代の人々は、その後ずっと活躍つづけているという事実に、後につづくはずの我々の世代は、何をしてきたか・・と疑問に思うことが時々あります。文学では、我々の世代では村上春樹がいますが、彼もまたアメリカ文学に造詣も深く、影響も受けていますが、彼の場合は、アメリカ文学の戦後あるいは同時代作家より、フィッツジェラルド、レイモンド・チャンドラーなど戦前の作家に影響されていることは、面白いですね。美術、造形、建築などでは、丹下健三が、アメリカ建築学会第1回太平洋賞を1958年に受賞しました。その後、東大の丹下門下からは槇文彦、磯崎新、黒川紀章の世代が出て、その後は伊東豊雄、隈健吾に至る現在まで、日本の建築家が、欧米はじめ広く世界で活躍する端緒を開いたのでした。彫刻家では詩人の野口米次郎とアメリカ人女性の間に生まれたイサム・ノグチは、日本的造形美を生み出し、日本で制作し、多くの日本人彫刻家に刺激を与えました。美術では、アメリカがむしろ日本の美術により深い関心を示し、ロックフェラー家の人々のように高い鑑賞力をもって日本美術を蒐集しています。今では、日本でも有名になった若冲に関心を持ち蒐集しているのはアメリカ人です。日本の版画には特に関心が高く、さきに紹介したベアテさんは、棟方志巧を米国に招いて、世界的に名声を博すのに支援しました。より広範な大衆的な分野では、アメリカの影響は更に絶大なものがあります。まず映画ですね。戦後、日本人で世界的にもっとも有名な人と言えば、黒澤明です。アメリカで出版された20世紀の文化現象を描いた分厚いグラフ書籍がありますが、その中で日本人では、唯一人、黒澤明監督が載っています。黒澤明自身は、アメリカのジョン・フォード監督の影響を受けたと言っていますが、確かに黒澤の映像の立体感、展開のスピード感は、アメリカ映画の標準以上だったことは、フォードの影響を自分のものにしたからと思います。「七人の侍」はアメリカでは「荒野の七人」」となり、「隠し砦の三悪人」の人物造形は「スターウォーズ」に使われました。「羅生門」は英語の舞台劇になっています。黒澤の「用心棒」を全面盗作した「荒野の用心棒」はマカロニ・ウエスタンの世界的ヒットを起こしました。その主役のクリント・イーストウッドはその後の活躍から「硫黄島からの手紙」の製作まで日本との関係は浅からぬものがあります。黒澤以外にも、1950年代の日本映画の黄金時代を築いた監督たち、小津安二郎、溝口健二、成瀬巳喜男など欧米で賞を取り、日本映画の価値を広めました。同時に日本映画が広く知られるようになったのには、アメリカ人のドナルド・リチーなどの優れた日本映画紹介者の功績も見逃せません。小津安二郎の世界は日本的で欧米人にはわかりにくいのではないか・・とも思われていましたが、家族をある種の建前で描くアメリカ人にとっては、小津の描く家族に、国や文化の違いを超えた普遍性を見出したのでしょう。黒澤が男性ジェンダーとすれば、溝口健二の世界は、女性ジェンダーと言えるでしょう。シカゴ大学で、両監督の特集映画祭がそれぞれありましたが、溝口の描く世界は、およそアメリカの大学生の生活環境とは異なるにもかかわらず、学生たちが真剣に見入り、深く感動しているのを目の当たりにしました。そして私の背後で、女子学生が、「黒澤より溝口の方が好きだ」と言っていたことを思い出します。
思わぬ映画が、アメリカ人の関心を集めた例は、「ゴジラ」です。一番初めの「ゴジラ」を今、見てみると、ビキニ環礁の放射能汚染で蘇った恐竜ゴジラによる都市の破壊、無策でただ頭を抱える政府の会議、女学生たちの犠牲者を悼む悲しい旋律の合唱、そして少数の主人公たちの必死の避難というこの四つのパターンが繰り返している映画です。でもその繰り返しの中には、明らかに、ついこの間まで体験してきた戦争の記憶が色濃く反映しているのが分かります。一方、アメリカにとっては、未知なるもの、巨大なるものへの恐怖と好奇心という、それこそ、アメリカ開拓以来のアメリカ人の原型心理が反映しているといえるでしょう。アメリカ人のゴジラへの関心は、ジュラシックパークまで続いてきているわけです。現在、宮崎駿のアニメーションは、世界的に多くのファンを獲得しています。私は、在外勤務で日本語のスピーチコンテストの審査委員を経験したことがありますが、中学生や高校生の、一般的に女子が多いですが、宮崎駿の肖像写真を見せながら「宮崎駿は私の英雄です」という日本語を話す子供たちに沢山出会いました。グローバリゼーションは、経済だけでなく、文化面でも既に始まり、日々進んでいるのです。
テレビのことも言及しないわけにはいきません。特に戦後世代である我々世代の子供時代は、アメリカ製テレビ番組は、まさしく娯楽の中心でした。「名犬ラッシー」やアメリカホームドラマでは「パパはなんでも知っている」、「ビーバーちゃん」など、そこで見た大きな家、大きな車、そしてカラーテレビやアイスクリームがいつでも食べられる大型冷凍冷蔵庫など、アメリカのホームドラマがもたらした豊かな生活のモデルは、日本の高度成長を支えた心理的動機と決して無縁ではありません。この現象は、日本だけかと長らく思っていましたが、同世代のドイツ人、英国人やフランス人が全く同じことを言っているのを聞きました。茶の間まで入り込んだアメリカ西部劇、ローハイドやララミー牧場など懐かしい名前を思い出す方も多いでしょう。こうしてみると、アメリカの番組で主人公になるのは男性が圧倒的に多いのですが、日本のホームドラマでは母親や女性一代記のように女性が多いことにも気づきますよね。この違いは、日米関係の役割の差とはむしろ関係の無い、それぞれの文化的背景を持った文化の現れ方の違いとでも言うべきものと思います。ただ、この文化の表現的性質とでも言うべきものが、現実の国同士の関係に反映しないとは言えないのです。
では、ここで知的・アカデミックな分野の交流―といっても人文系に限っての話ですが―について、概観してみます。戦後の米国の民間財団による大学や研究所、図書館など知的分野への支援が終了する頃、今度は日本側がアメリカの日本研究の支援を開始しました。1973年7月末に訪米した田中角栄首相は、全米の10の大学に各100万ドルの日本研究のための寄贈を行いました。これにより米国における日本研究の道筋が作られ現在に至っています。
知的交流を歴史的に見てみますと、戦後の米国の日本のアカデミー支援の目的は、日本の民主化でした。そして民主化の過程を「日本の近代化」論に結び付けて論じたのがライシャワー博士でした。ライシャワー氏は、1960年の日米安保条約改訂の際の、日本で起きた大きな政治運動、反安保、反米の動きを憂慮して「日本との損なわれた対話(Broken Dialogue with Japan)」と題する論文を1960年10月号のフォーリン・アフェアーズ誌に発表しました。これがケネディ政権のスタッフの目にとまり、ハーバードで教鞭をとっていたライシャワー氏は駐日米国大使に任命されたのです。これはいささか感想めいたものですが、ケネディ大統領は米国史上、初のアイルランド系でカソリックの大統領ですが、アイルランド系であるが故に、ライシャワー氏の論文を理解するところが深かったのではないでしょうか?不本意にあるいは理不尽に劣位に置かれた人々の気持ちへの想像力があり得たのではないかと想像するのです。米ソが着々と進める冷戦体制に、当時の日本人が恐れたのは米ソの戦争に巻き込まれるのではないかという危機感であり、民主的な十分な議論がされていないという怒りでした。このことをライシャワー氏は指摘しながら、激しい反安保デモの中でも、アメリカ人である自分が身の危険を感じるようなことは何もなかったと述べています。
「日本との損なわれた対話」の論文より先に60年の夏にライシャワー博士は「日本の近代化」に関して、日米の知識人が一堂に集まった会議を箱根で開催しました。その会議には日本からは蝋山正道、高坂正顕、丸山真男、加藤周一、永井道雄、遠山茂樹など右派、保守、リベラル、左派、マルキストまで幅広い知識人が参加しています。ライシャワー氏の考えを概略すれば、日本は歴史的に近代化を達成したが、その過程は欧米の段階よりやや遅れている、その日本の近代化の段階を議論しようとするものでした。この議論は、更に1965年から日米の知識人同士の対話「近代日本に関する会議」として5年間続きました。
しかし、60年代後半から70年代全般に世界的に沸き起こったステューデント・パワーの時代に、「近代化」論に大きな批判が若者から起きたのです。前に紹介しました「敗北を抱きしめて」のジョン・ダワー氏らの若手日本歴史研究者が、各国には独自の文化、歴史があり、それを尊重すべきだとして、西洋中心の基準による一律の近代化論を批判したのです。開発、発展、近代化、合理主義などの概念に対する批判は、ヴィエトナム戦争にアメリカが勝利しなかったという現実の状況と反戦、厭戦の思いがまじりあった状況が生み出した新しい概念だったのです。日本でも、類似の、例えばそれまで代表的進歩的知識人の丸山真男批判が展開しました。
40年前に盛んになった「近代化」その是非論争は、いまだに決着をみていませんし、いや、むしろ、今日では、まさに「遅れた近代化」の大国―インドや中国が経済発展という「近代化」路線を突き進んでいます。と同時に世界的な近代化の負の遺産としての地球環境問題など、「近代化」論は、一層切実な問題となっています。今では、この問題は、二手に分かれて単なる是非で論争するのではなく、未来へとつなげる解決力が求められているとも言えるでしょう。
それでは、ここで、現在までの日米双方の相手のイメージの変遷を見てみましょう。まず、終戦直後から50年代は、米国にとって日本は「か弱く従順な女性」でした。一方、日本にとってのアメリカは「頼りになる強力なボス」でした。皆さん、ボスという名の缶コーヒーのあの顔は、どことなくマッカーサーを思わせませんか?サングラスにパイプ・・マッカーサーはコーンパイプでしたから同じではありませんが、イメージが似ていますね。あのコマーシャルで面白いのがありました。おしぼりで顔を拭きながら、サラリーマンの男性が「日本もアメリカにガツンと言ってやりゃいいんだよ、俺なら言うね」と言ったところに、クリントン大統領のそっくりさんが出てきて「ガツンとは何だ?」と訊くと、驚いたままゴクリと缶コーヒーを飲む・・というCMです。あの「ガツンと言ってやる」というセリフは、おそらく日本人男性なら、一度はどこかで言ったことのあるセリフではないでしょうか。
さて、徐々に経済力が上がってきた日本は「メガネをかけてカメラをぶら下げた背広の男性」のイメージになっていきます。一方日本にとってのアメリカは「日本製品に金を惜しまない気前の良い消費者」でした。しかし、バブル景気に沸く日本は「アメリカを脅かす企業戦士」となり、日本にとっては「自己中心的な要求ばかりの上司」であるアメリカから、いまでは「衰えていく大国」のイメージになりつつあります。一方、アメリカにとっての現在の日本は「多種多様な文化をもつ日常的存在」となりつつあります。こうしてみると、現在のアメリカにおける対日イメージが、ジェンダーフリーになっていることと、終戦直後の女性イメージ以外、双方のイメージは、男性イメージがむしろ支配的であることに気が付きます。双方が互いに男性イメージを持ってくると、そこには競争や勝敗、優劣などの原理が働きがちになります。もちろん、女性にも競争原理が無いとは言えませんが、社会的、集団的広がりの観点からは、競争原理は男性的と言えるでしょう。
この男性ジェンダーの視点から、より明確に言えば、日本人男性の視点から日米関係をみると、「悪いのはアメリカ」という安直な結論になりがちです。私は「アメリカは悪くない」と言うのではありません。アメリカも日本を男性とみなし始めると途端に、不信感に身構える傾向があります。いずれにしても、自己省察なしに他に原因を押し付けても、問題の解決にはなりません。例えば、日本のリベラルな論客には、戦後のアメリカの民主化政策が、冷戦体制で、十分徹底化されなかったから、日本の民主化は不十分という議論がありますが、戦後も65年以上たった今、民主化の話は、もはや我々自身の問題のはずです。また、保守派では、日本の伝統的な価値をアメリカ文化が破壊したというような相変わらず繰り返される議論がありますが、これも、継承すべき伝統や価値は、我々が考え行動すべき問題であって、アメリカ人に日本の伝統文化や価値の継承を期待しているわけではないはずです。最近、私が驚いたのは、テレビのコメンテーターなどが、いともたやすく「民主主義は駄目なんです」と発言することです。一体、そう発言する彼や彼女は、民主主義にかわる政治体制になにを考えているのでしょうか?独裁政治、貴族政治あるいは寡頭政治?・・では、彼らは、そのごく少数の支配層に自分は入るという自信と根拠はどこから来るのでしょうか?それとも、多数の支配される側になりたいのでしょうか?民主主義の根幹である参政権は・・、誰かに譲ってもいいのでしょうか?あるいは、他の人の権利を奪いたいのでしょうか?その根拠はなんなのでしょう。特に女性の参政権は、わずか66年前に獲得したに過ぎないのです。そんなに簡単に捨てても良いのでしょうか?
民主主義が、期待通りに機能しないことと、民主主義がダメとか間違っているとかは、全く次元の違う問題です。もし、「いや、機能しないことを駄目と言っただけ」と言う人がいたら、その人は民主主義の恩恵に浸りすぎた無自覚な人で、言葉づかいも知らない人・・ということです。
最後に、二人のアメリカ人のエピソードを紹介したいと思います。一人は、最長期間の駐日大使を務めたマイク・マンスフィールドさんの話です。大使時代、来客には必ず自らお茶をだしていた・・ということですが、これは、日本人が女性にお茶くみをさせていることの反対表明だったとのことです。一見、アメリカ人のおせっかいとも思えますが、実は、マンスフィールド大使の女性観には、モーリン夫人との出会いが深く関わっています。マンスフィールドさんは、上院議員当時からアカデミックな人としても知られていましたが、決して裕福な生まれではなく、十代で年をごまかして海軍に入った後、炭鉱で働いていた時に、モーリンさんと出会ったのです。モーリンさんは、その地域の裕福な家族の出身で、自身は教師をしていましたが、ある日、背の高いマイク青年が丘を登ってくるのを見た時「この人と一生を共にする」と思ったというのですから、いわゆる一目惚れですね。そして彼に、高等教育への進学を勧め、支えたのです。モーリンさんとの出会いが無かったら、マンスフィールド上院議員も駐日大使もなかったのです。大使は、生涯、夫人を大切に尊重し、自分が関与する団体の名前には常に夫人と自分の名前を刻んだと言います。マンスフィールド大使にとっては、お茶くみは女性のするもの・・とする日本の社会慣行は受け入れ難かったことは容易に想像できます。

さて、もうひとりは、1916年女性で初の連邦下院議員となった共和党のジャネット・ランキンさんのことです。この人は、1917年に、米国が第一次世界大戦に参戦するのに唯一人反対票を投じました。そして1941年、真珠湾攻撃後のアメリカの第二次世界大戦参戦は、やはり唯一人反対しました。そして、1968年、ヴェトナム戦争反対のため、ワシントンD.C.までのデモ行進を率いました。生涯、平和主義を貫いた女性です。ランキンさんは、60年代、70年代のフェミニズムの新しい波世代から尊敬の対象とされました。女性だから、平和主義になれたのだと言う人がいたら、それなら、もっと女性を政治の場所に出すべきではないかと尋ねたいです。
さて、結論ですが、日米に限らず、言語や文化の異なる国同士、あるいは人間同士が理解する上で、何がもっとも有効で重要かといえば、芸術・文化であると確信します。その理由としては、芸術や文化は、例えばジェンダーという人間の根幹であると同時に繊細で複雑な心理を伴う問題にも、自ずと関わっているからです。また、食文化のようにジェンダーを超えた人間共通の文化もあります。芸術や文化は、人間が「体験」できるものなのです。そして、その体験は、人間と社会の複雑性への想像力を養ってくれます。また、最初は、感覚的刺激から出発しても、文化や芸術を通しての感動は、たいていの場合、記憶として残ることで、落ち着いた持続的思考へと導いてくれます。そして、ジェンダー、性別や性差を超えた人間共通の心理や真実を経験させてくれます。また自分とは異なるジェンダーの経験をすることも、認識することも可能です。例えば、我々は文学や映画を見ながら、主人公に、自分と性は違っていても、自己同一化:アイデンティフィケーションがごく自然にできるでしょう。おそらく、それは実生活では不可能なことですが、芸術と言う抽象世界の中では可能になるのです。その経験が、また実生活で生かされることにもなります。ジェンダー間のより良いコミュニケーションを実現することができます。その上で、異性同士の知的で創造的な対話が、幅広い分野で可能になるでしょう。
これは、個人同士は無論のこと、もっと大きな単位の人間集団や国同士にも該当するのではないかと思っています。
ご清聴ありがとうございました。
ベアテ・シロタ・ゴードンさんは、昨年12月30日にニューヨークのご自宅で逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を捧げます。
注:
(1)「シャドウ・ワーク」I・イリイチ、玉野井芳郎、栗原彬訳 岩波書店1982年
(2)”Embracing Defeat; Japan in the wake of World WarII” John W. Dower, W.W. Norton & Company, 1999,「敗北を抱きしめて」ジョン・ダワー、三浦陽一、高杉忠 明訳 岩波書店 2004年、2009年
(3)「戦後日米関係とフィランソロピー:民間財団が果たした役割、1945年~1975年」山本正編著、ミネルヴァ書房、2008年
(4)「1945年のクリスマス;日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝」ベアテ・シロタ・ゴードン、平岡磨紀子(構成・文)柏書房 1995年
(5)”The Only Woman In The Room; A MEMOIR” Beate Sirota Gordon, Kodansha International 1997, 2001
越智淳子
早稲田大学第一政経学部卒。フリーランスジャーナリストとして毎日新聞出版部、政治部などで仕事の後、ジャパンエコー社(英文出版社)勤務。1980年外務省入省と同時に在シカゴ日本総領事館にて広報文化を担当。以後、在外勤務では英国、ノルウエー、ハンガリー、フィンランドの日本大使館で広報、日本紹介、文化交流に携わる。海外での日本文化紹介事業としては最大規模のジャパンフェスティバル1991(英国)に一貫して関与し、ノルウエーでは、オスロのウルティマ現代音楽フェスティバル日本特集の実現に関与するなど、各国で伝統文化から現代作品まで日本文化を幅広く紹介してきた。外務本省では、国際報道課、西欧第二課、人権難民課に勤務。国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター(IETC)上級審議官(2003~2005年)。在ポートランド日本総領事館を最後に外務省退職。その後、ポートランド州立大学国際客員講師(2009夏期)、ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所日米関係プログラム研究員(2009~2010)。現在、早稲田大学アジア研究機構アジア・北米研究所招聘研究員。大岡信ことば館アドバイザー。国際交流、文化交流に関する講演、助言等を行っている。


